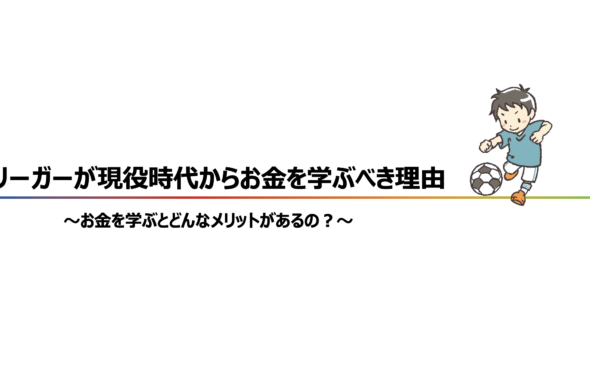減価償却は節税にはならない?
会計や税金、不動産の勉強をしているとよく「減価償却」という言葉を耳にすることがあります。
普段の生活では馴染みのない言葉ですが、特に個人の方では不動産投資を行うと必ず聞くことになります。
一般的には「減価償却で節税ができる」と言われたりもしますが、実際には売却時により多くの税金を払うことになる可能性があるなど、減価償却は理解するのが難しい仕組みです。
しかし、手元のキャッシュを厚くして資産形成や資産防衛をすることができるなど、お金持ちになるためには減価償却をしっかり理解しなければいけません。
そこで、本日は減価償却について紹介したいと思います。
■減価償却ってなに?
不動産投資などを行うと必ず出てくる言葉に「減価償却」というものがあります。
経営者の方などであれば聞いたことがあるかもしれませんが、会社員の方などは馴染みがない言葉だと思います。
減価償却とは、簡単に言うと「費用の振り分け」です。会計の世界で使われるのですが、例えば不動産や車、機械のように長持ちする資産であれば、分割して費用計上するのが適切ではないか、という考え方です。これらの資産は1回限りで使い捨てをするわけではなく、長期に渡って使用していくものになります。しかし、長年使っていくとその資産の価値は時間の経過分だけ下落していきます。
そういった資産を取得した際には、取得したときに一括で費用として計上するよりも、使用可能期間に渡って分割して費用計上する方が理に適っているだろう、ということになります。
具体的に言うと、10年間は使い続けられる機械を100万円で購入したとします。そうしたら、購入年度に100万円を費用計上するよりも、10年間に渡って10万円ずつ費用計上した方が適切だろう、という考え方が減価償却です。
■償却できる期間は法定耐用年数で決まっている
では、この減価償却の際にはどのくらいの年数に分けて費用計上すれば良いのでしょうか。
償却できる期間は法定耐用年数というもので定められています。
つまり、その資産を使い続けられるであろうと定められた年数が決まっています。不動産の場合は、新築か中古か、あるいは構造によって、耐用年数が定められています。
例えば、不動産の法定耐用年数は以下のように決まっています。
軽量鉄骨造 19年
木造 22年
鉄骨造 34年
鉄筋コンクリート造 47年
ちなみに、土地は経年劣化しないので、減価償却の対象外となります。法定耐用年数の範囲内で計算された減価償却費は、不動産投資についての確定申告をする際に費用計上することになります。
■減価償却で税金が減る?
ちなみにこの減価償却をうまく利用すると、会社員の方で不動産投資をしている方などは、税金の還付を受けることが可能です。
減価償却分や不動産投資に使った諸経費を経費計上することで、実際のキャッシュフローは黒字でも会計上の赤字を作り所得を減らすことができるからです。
ただし、ここで気を付けなければならないことは、減価償却は「税金の免除」ではないということです。
どういうことかと言うと、不動産を売却する際に、減価償却費の分だけ取得費が下がるということです。
具体的に見てみましょう。
例えば、当初の取得費が3,000万円の物件が2,500万円で売れたと想定します。
すると、この場合の利益は取得費-売却価格=-500万円となり、課税されることはありません。
しかし、この取得費は減価償却の分だけ減少させなければいけないというルールがあります。
仮に、上記の例で減価償却を1,000万円分していた場合、取得費は2,000万円で計算することになります。
すると、取得費-売却価格=500万円となり、この利益に対して課税されることになります。
上記の例のように、減価償却で計上した分は取得物件の簿価に影響するため、将来その不動産を売却した際に多く税金を払うことになるため注意が必要です。
このような注意点はありますが、税金の還付で手元のキャッシュを手厚くすることができ、うまく使うと資産防衛や資産形成に役立ちます。
特に高い税率を払っている方ほど、この仕組みを有効に活用することができます。
少し難しい概念ですが、今後不動産投資をやってみたいという方は、ぜひ知っておいていただければと思います。
_透過-1.png)