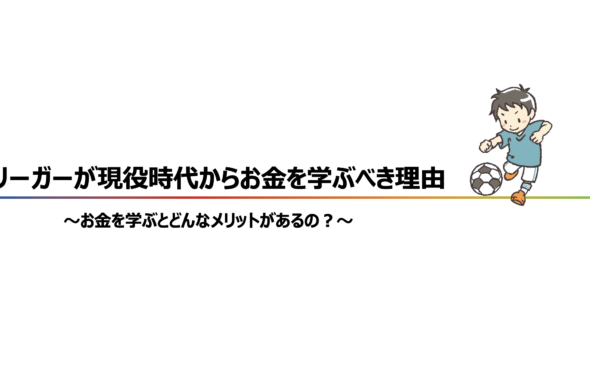金融庁が教えてくれた、買ってはいけない金融商品トップ3
金融庁といえば、日本の金融を取りまとめている国の公的な機関です。
日本のすべての銀行、保険、証券会社等を取りまとめている親玉でもある金融庁ですが、1年に1度、日本の金融についてまとめた「金融レポート」というものを発表しています。
その金融レポートの中で、投資家が買うべきではない3つの商品が紹介されているのはご存じでしょうか?
国も警告をするほどオススメできない金融商品とは一体なんなのか。
本日は、金融庁の金融レポートの中から投資家が買ってはいけない金融商品の3つを紹介します。
■毎月分配型投資信託
毎月分配型の投資信託とは、文字通り“毎月”分配金がもらえる投資信託です。例えば、「100万円投資をすると毎月1万円の分配金が受け取れる」というものがこれにあたります。
これだけ聞くと「毎月お金がもらえてお得!」と思われがちですが、その分配金は運用資金から支払われています。
つまり、運用で利益が出ていれば、その利益から分配金の一部(もしくは全額)が支払われるので良いのですが、多くの場合は自分が投資信託を購入するときに支払った代金の一部が戻ってきているだけなのです。
そして、その影響で運用資金が減ってくると、分配金の額も減ることになります。
簡単に言えば、払ったお金が自分に返ってきてるだけで基準価額(自分が持っている投資信託の価値)はどんどん下落していくことになります。
この仕組みでは複利効果も活かせないので、資産形成としても商品性としても最悪です。
よほどの理由がない限り、こういうタイプの投資信託は絶対に買うべきではありません。
■個人年金保険(特に外貨建てのもの)などの貯蓄性保険商品
外貨建て保険は友人などに紹介された保険屋さんに勧められて加入してる人は多いのではないでしょうか。
貯蓄性のある保険は、「万が一に備えつつお金も貯められて一石二鳥ですよ」と営業マンに言われ、かつ銀行預金より高利回りなこともあって多くの方が契約してしまいがちです。
一見、万が一の備えもできて貯蓄ができるというと非常に効率が良い商品と思われがちですが、機能を複合的に併せ持っているがゆえに保険としても、貯蓄としても、資産形成としても中途半端で質が悪いものとなっています。
そして、もうひとつの問題点として手数料の高さがあります。
商品によって異なりますが、例えば外貨建て保険などでは契約金額の7~10%が手数料として金融機関の収益になるものも多いようです。
一般的な投資信託の購入時手数料が2~3%ということを考えると、外貨建て保険をはじめとする貯蓄性のある保険は手数料が高く、投資家にとってはデメリットが大きい商品だと言えます。
■ファンドラップ(ラップ口座)
ファンドラップは、投資一任運用サービスの一種で、私たち投資家のリスク許容度や投資目的に合わせて、金融機関の専門家のアドバイスをもとに異なるタイプの複数の投資信託(ファンド)を選び、これらを組み合わせて運用するサービスをいいます。
具体的には、運用前のヒアリングから、投資方針の提案、実際の運用、報告や見直しまで、トータルなサービスが受けられます。
一般にファンドラップと似たようなサービスとして「ラップ口座」がありますが、最低運用額(契約金額)が数千万円~数億円程度の設定が多く、富裕層が対象です。これに対して、ファンドラップは、契約金額が数百万円から利用できるものもあり、ラップ口座と比べて利用しやすくなっています。
ファンドラップやラップ口座を分かりやすく言うと、ある程度まとまったお金の運用を丸ごとプロにおまかせする、というサービスです。
ラップ運用(特にファンドラップ)の問題点は、なんといっても手数料の高さです。
日本のファンドラップは「手数料の塊」と揶揄されるほどで、ファンドラップの顧客が負担する手数料は平均で年間2.2%という高さです。
一般的な投資信託の信託報酬の平均は1.5%なので、長期で見れば見るほど運用結果の差は大きくなります。
当たり前ですが、金融商品を選ぶ際は手数料を安いものを選ぶことは大前提です。
ファンドラップは、その口座そのものの手数料と投資先のファンドの信託報酬が二重でかかっています。よほどの理由がない限りはファンドラップは利用しない方が良いでしょう。・・・
金融庁が警告する買ってはいけない3つの金融商品を紹介しましたが、これらは金融知識があれば分かる事です。
金融知識がないからプロや他の人の言いなりになってばかりでは、結局最後に損をするのは自分です。
適切な金融商品を選ぶためにも、最低限のお金の勉強はしていきましょう。
_透過-1.png)