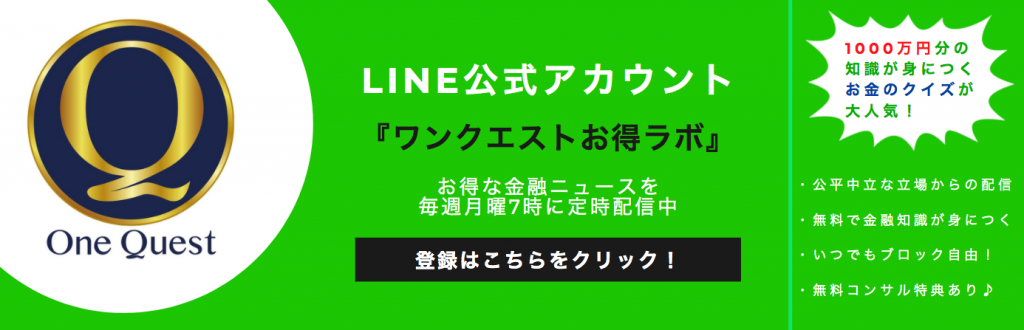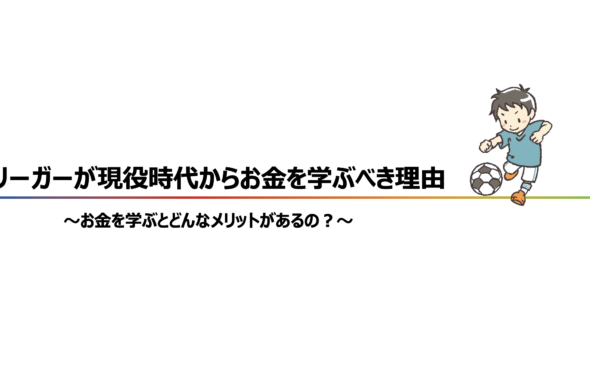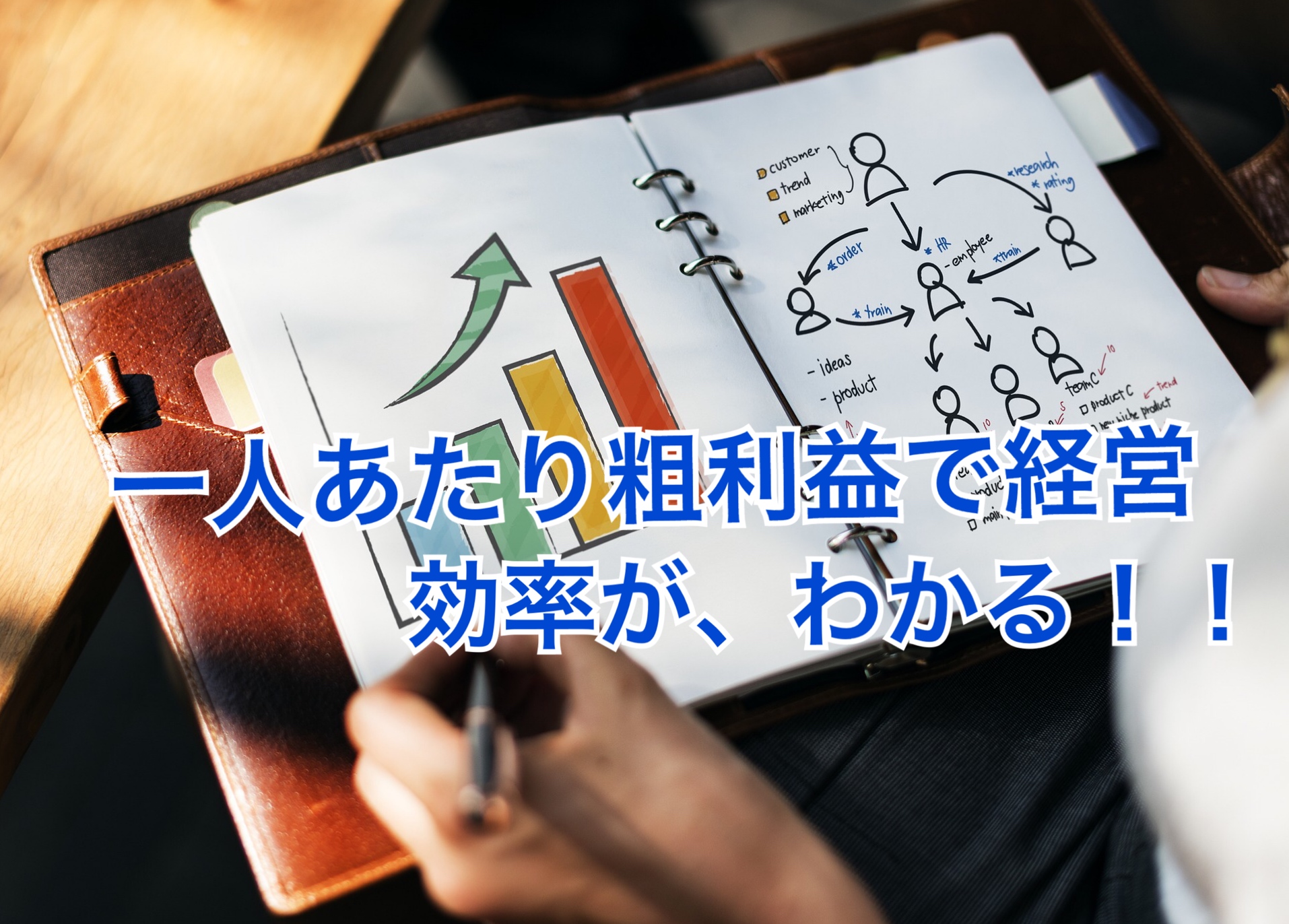
一人あたりの粗利益で経営の効率がわかる!!
「どうしてこんなに給料が安いんだろう」
このようなことは、誰しもが一度は思ったことがあるのではないでしょうか?
私も含め、給料を貰う方にとってはお給料はたくさん貰いたいですよね。
一方、会社から見ると人件費は大きな出費です。私たちの給料(人件費)の源になっているのは会社の利益ですから、利益が上がらないことには給料が上がることはありません。
会社を経営する上で見る指標というのは、様々なものがあります。売上高、粗利益、営業利益、税引き後当期純利益などが挙げられますが、冒頭の人件費に関わる指標の一つに「一人当たり粗利益」があります。
一人当たり粗利益とは一体なんなのか。
本日は会社の生産性について考えてみます。
■なぜ一人当たり粗利益が大事なのか
一人当たり粗利益とは、従業員一人当たりがどれだけの粗利益を稼いだかを判断するための指標です。
つまり、この指標を見れば会社にいる人員(社員さんたち)がどのくらい効率的にお金を稼ぐことができているか(効率的に収益を挙げているか)が分かります。そして、その数字からは社員さんが貰うことができる給与の限界値も見えてきます。
例えば一人当たり粗利益が1,000万円の会社があったとします。粗利益とは売上から仕入れの原価を引いた「売上総利益」のことですので、企業が稼ぐことのできる限界の利益ということになります。
この粗利益の中から人件費、管理費など様々なお金を支払わなければならないため、一人当たり粗利益が1,000万円の会社で社員の方々の平均年収が1,000万円に達するということは絶対にありません。
■目安はどれくらい?
一人当たり粗利益は、次のような算式で求めることができます。
粗利益(売上総利益)÷社員数=一人当たり粗利益
日本の平均はおおよそ600万円程度と言われているので、一度お勤め先の数値で計算してみてください。
それでは一人当たり粗利益はどのくらいが目安になるのでしょうか。会社の規模、業種によっても異なりますが、一般的に多く言われているのは次のような金額です。
最低ラインの目標
→1,000万円
できればの目標
→1,500万円以上
上場企業など高収益企業
→2,000万円以上
上場企業は2,000万円以上の一人当たり粗利益があることが多いと言われています。人件費の割合が一人当たり粗利益の3割だとすると、平均年収は600万円ということになりますね。
中小企業では上場企業に比べると給与が低い場合が多いと言われていますが、一人当たり粗利益が小さい会社では年収が高くなることはありません。
■給与の3倍の粗利益を
企業にとっては、社員を雇うことは大変な出費になります。社員1人雇うとかかる経費、営業活動費、様々な管理費、さらには資金調達の費用なども考えれば、給料の3倍の粗利益が必要とも言われています。給料や賞与に法定福利費や福利厚生費、さらには通勤手当などの経費も加えた人件費に対しては、最低でも倍の粗利益を稼がなければなりません。
もちろん営業の方と事務の方とでは稼ぐべき粗利益は変わってきますが、全体をならしたときに給与の3倍くらいの一人当たり粗利益がある会社は健全である、と言えそうです。
会社の経営者の方で社員さんを雇用しているという方も、ぜひ一人当たり粗利益、つまりは一人当たりの生産性は意識してみてください。これを意識していくと強い会社が作れるのではと思います。
_透過-1.png)