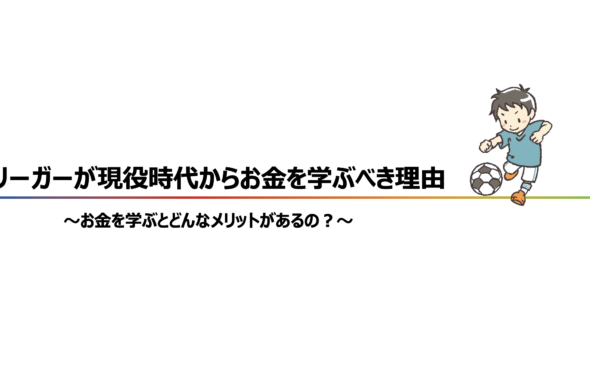これから結婚、出産する人に知ってほしい社会保障制度①~出産手当金~】
20代後半に差し掛かり、私の周りでも結婚をしたり子供が生まれるという友人が増えてきました。
最近は妊娠・出産をしても、産休、育休を取得して会社に復帰する女性が増えています。
休職し、子育てに専念できることは素晴らしいことですが、その一方でご自身の収入のことが気になるという方は多いと思います。
そこで、今回は産休、育休中にもらえる社会保障制度にはどんなものがあるのか、3回にわたって紹介します。
初回となる本日は、出産手当金についてお伝えしていきます。
◼出産手当金を受け取れる条件
「出産手当金」は「産休手当」と呼ばれることもある、産休取得中にもらえるお金のことです。
一言でいうと、産休中の収入を保障してくれる社会保障制度です。
出産手当金の対象になるのは、勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人や、一定の条件を満たして退職した人です。
正社員だけでなく、自分で健康保険の保険料を支払っている契約社員、パート、アルバイトなども対象に含まれます。
一方、国民健康保険の加入者や、家族の扶養に入っている人は対象ではありませんので、自営業の方などは注意が必要です。
そして基本的に、「出産のために仕事を休み、給料が会社から支払われていないこと」が条件です。もし給料が出ている場合でも、出産手当金よりも給料が少ない場合にはその差額分が支払われます。
出産手当金は正常な分娩ができなかったケースでも、妊娠が4ヶ月(85日)以上継続していれば支払われます。
つまり妊娠4ヶ月を過ぎて、流産、早産、死産や、人工中絶となったケースでも出産手当金は受け取れます。
出産に伴って退職をする場合にも、以下の3つの条件をクリアすれば出産手当金は受け取れます。
・健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
・出産日もしくは出産予定日から42日、多胎妊娠の場合は98日以内に退職していること
・退職日に働いていないこと
3つ目の条件の、退職日に働いていないことの要件を満たしていないために受け取れない人が多いので注意が必要です。
◼出産手当金がもらえる期間
出産手当金は出産日が予定日より遅れた場合と、早くなった場合で支給日数が違います。はっきり言えば予定日以降に生まれたほうが多く受け取ることができます。
出産日以前の42日から出産日の翌日以降56日までの合計98日間分の支給を基本として、以下の計算式により支給日数は増減します。
・出産予定日より早まった場合
42日(多胎は98日)-α日(早まった日数)+56日(産後休業日数)
・出産予定日より遅く生まれた場合
42日(多胎は98日)+α日(遅くなった日数)+56日(産後休業日数)
◼もらえる金額はどれくらい?
1日あたりの受給額は、
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3
という計算式で算出されます。
非常にわかりにくいですが、標準報酬月額とは、毎月の基本給と、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたもののことをいいます。
難しくてよくわからないという方は、「給料の3分の2がもらえる」と覚えてもいいと思います。
たとえば、東京都で給料が各種手当を入れて21万円の場合、標準報酬月額は20万円になります。
出産手当金の計算に必要なのは12ヶ月間の標準報酬月額を合算して平均したものです。
この例を上記の計算式に当てはめると以下のようになります。
20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円(1日あたりの支給額)
予定日通りに出産した方は、98日分が支給されるので、上記に98日を掛けます。
約4,444円 × 98日(受け取れる日数)=約435,512円(受け取れる出産手当金の総額)
このように計算を行います。
出産手当金の計算では「標準報酬月額の平均」と「受け取れる日数」がポイントになります。
出産のために退職される方は、前述の退職時の要件を満たしたうえで退職するようにしましょう。
_透過-1.png)