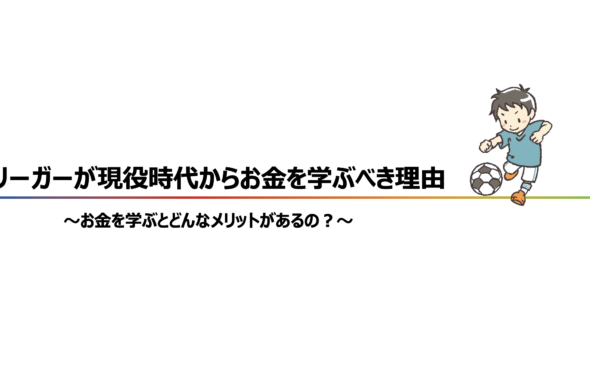世界的株安 原因と今後取るべき行動
昨日は世界の株式市場が荒れた一日となりました。原因は米国の金利上昇に端を発した米国市場での株式の急落です。
米金利上昇が原因となる株安は2月、4月に続いて今年で3度目ですが、今回が違うのは、長期金利が7年半ぶりの水準まで急ピッチに上昇したということです。
本日は、今回の株安の原因と今後について考えてみます。
■一時、日経平均株価が1000円超の下落
10月10日の日経平均株価の終値は23,506.04円でしたが、10月11日には安値が22,459.02円と一時1000円超の下落となりました。
この下げ幅は今年3番目の大きさで、テレビのテロップでも報道されるほどのものでした。
この下落の原因は、10日に米国株価が大幅な下落をしたことです。それにつられて、翌11日の日経平均も下落しました。
株価下落は米国や日本だけでなく世界的に発生していて、10月になってから世界の株式時価総額は約400兆円ほど消失しました。
なぜこのような株安が引き起こされたのでしょうか。それは、前々からテーマになっている
・米国の金利上昇
・対中貿易摩擦
これらが影響していると言われています。
■2つの原因と詳細
金利に関して言えば、2015年12月以降のFRB(米連邦準備制度)による利上げによって、米国では金利がかなり上昇してきています。
現在米国の10年国債の金利は3%を超えています。
金利が上がると株式に投資をする人が減るほか、企業が資金を調達する際の借入金利が上昇するために企業業績が悪くなる見通しが先行するため、株価が下がる傾向にあります。
実際に、2000年のITバブルや07年の住宅バブル等、過去を見ると米金利の上昇が株式や不動産などの資産価格を下落させて景気後退への引き金を引くパターンが多くありました。
さらに、米国は絶好調でも米国以外の欧州や新興国の景気は減速しており、米金利上昇のショックが世界景気や株価に悪影響を及ぼしやすくなっています。
中国との貿易戦争に関しては前々から言われている通りですが、8月の米貿易赤字が6カ月ぶりの高水準で、中でも対中赤字は過去最大となりました。
追加関税を実施するのとともに、中国の通貨である人民元安が進んでいることで、中国の貿易における競争力は維持されているようです。
当然米国にとっては面白くない結果ですから、11月の中間選挙に向けてさらに関税をかける話が進んだり、通貨戦争に発展するようであればさらなる混乱を招く可能性もあります。
■この状況でどう行動するか
このように、米国をめぐる懸念によって、日本を含め世界的に株安に見舞われました。
とはいえ、急落の後には割安な株が増えるのも確かなので、買いたかったけど少し割高だと考えていた株があるならばこのタイミングで買ってみても良いかもしれません。
また、投資信託等を定時定額購入している方にとってはこの下げ相場はまさにメリットの部分が最大限活かせるチャンスです。相場下落に一喜一憂せず、長期的な視野で投資を継続していけたらいいですね。
ただし、急落は一回で終わらずにもう一度大きな下げが来ることも多いですし、株式市場が荒れれば、為替も他の資産の価格も荒れることが予想されます。
しばらくは荒れる株式市場に警戒をしつつ、どんな状況にも対応できる体制を整えておきましょう。
_透過-1.png)