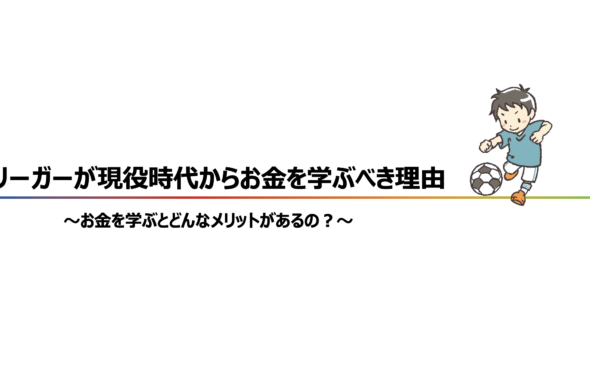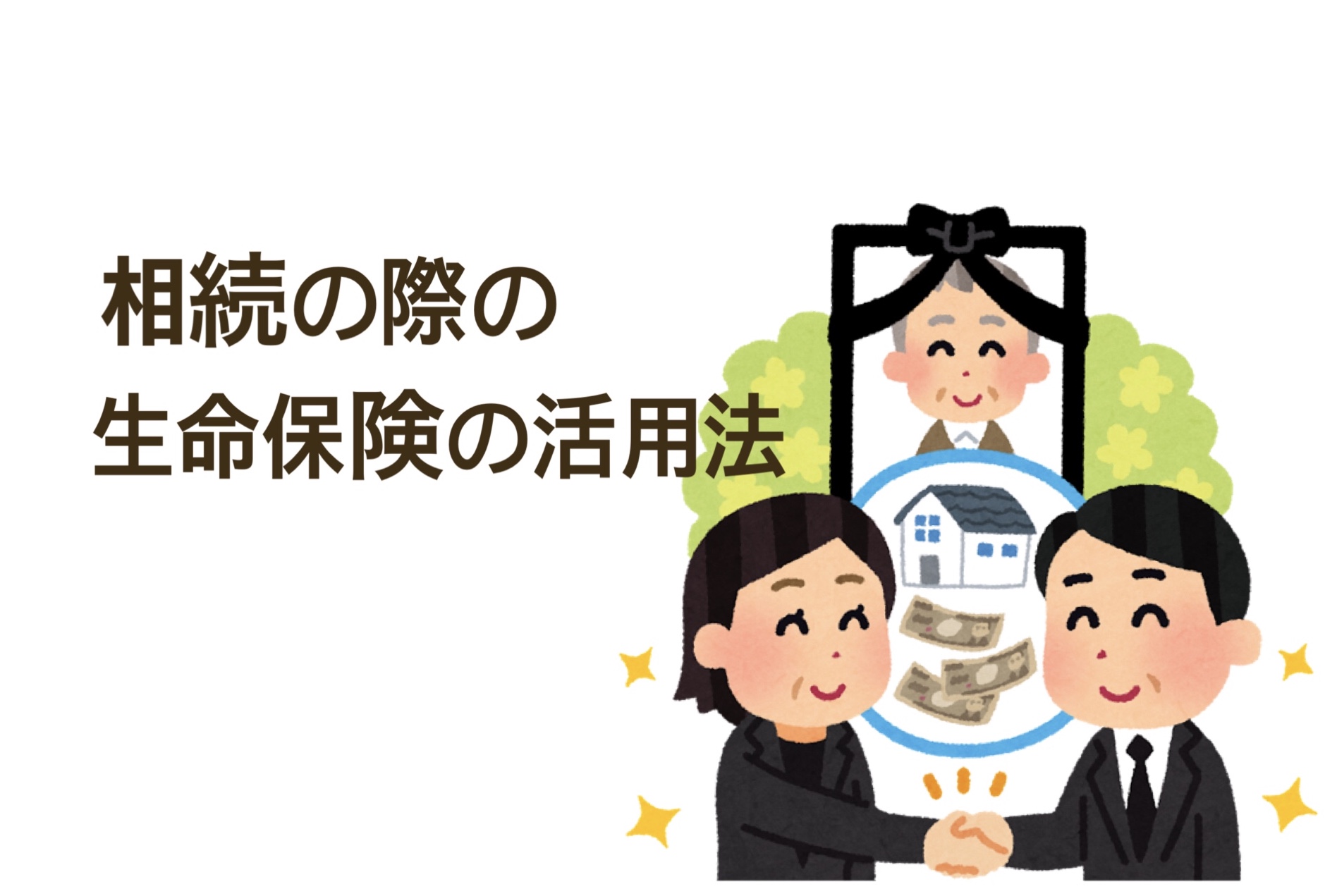
相続の際の生命保険の活用法
「生命保険」と聞くと、万が一自分が亡くなってしまった時に大きなお金を残すことができるもの、というイメージをお持ちの方は多いと思います。
しかし、生命保険が活用されるもうひとつの場面をご存知ですか?
それは、相続です。
今すぐ相続が起こらないという方でも、いつか必ず相続は発生します。
本日は相続において生命保険がどう役立つかについてご紹介します。
■生命保険には非課税枠がある
相続における生命保険の活用法のひとつに、生命保険の非課税枠があります。
被相続人(相続をされる人)が亡くなったことによって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
しかし、生命保険の死亡保険金は通常の相続の非課税枠とは別に、生命保険専用の非課税枠があります。
死亡保険金の受取人が相続人(相続をする人)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額までであれば相続税は非課税になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、4人家族のご主人が亡くなったとします。奥さんと2人のお子さんがいらっしゃる場合の法定相続人は3人です。この場合、生命保険の非課税枠は500万円×3人で1,500万円になります。
つまり、1,500万円までの保険金が非課税になるということです。
■みなし相続財産という仕組みを活用する
保険を活用することで非課税でお金の受け渡しができるのは分かりやすい例ですが、「みなし相続財産」という扱いを活用できるとさらに上手に相続を行うことができます。
保険金は通常の相続財産とは分けられ「みなし相続財産」という扱いをされます。
この「みなし相続財産」であるという特性上、保険金は指定されていた受取人に直接お金が入ることになり、被相続人の相続手続きにおける遺産分割協議で分ける必要がない財産になります。
簡単にいうと、相続における保険金は相続人みんなで分ける必要がないお金ということです。
この特性を活用することで、特定の相続人に対して一定額のお金を遺したい場合には、争いのもとになる遺産分割協議にのらない財産として保険金という形でお金を遺すことができます。
この仕組みによって、家族間の争いを未然に防いだり相続税の準備などをする方は多くいらっしゃいます。
■相続対策で生命保険を活用
上記の非課税枠やみなし相続財産としての生命保険の特性は、上手に使うとかなり活用できるものになります。
相続対策は亡くなったり認知症になってからでは何も手だてを打つことはできません。
これから発生することが確定している相続の対策として、生命保険を活用するという方法は非常に有効なものになります。
もし将来的な相続対策を考えている方は、信頼のおける経験豊富な税理士や生命保険のプロに相談してみると良いかもしれません。
そのような方が身近にいないという方はお気軽にご相談いただければと思います。
_透過-1.png)