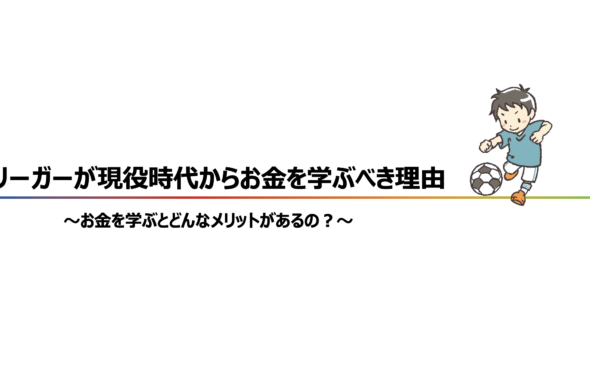若年世代の奨学金返済と将来対策のコツ
- 皆さんは大学の学費をどうやって工面しましたか?
「両親にお金を出してもらった」という方が多いと思いますが、今は大学・大学院の進学者の約4割が奨学金を利用しています。実際に、この記事を書いている私も奨学金を使って大学に通いました。
私たち若い世代は結婚やマイホーム購入などの資金需要が控える年齢層だけに、奨学金返済とうまく付き合いながら貯蓄を増やしたり資産形成をしていくことが大切です。
そこで、本日は奨学金の返済と将来対策を両立させるコツについて考えてみます。
◼️利用者は20年前の約4倍
日本学生支援機構によると、2016年度の奨学生の数は131万人で大学生や大学院生などの38%を占めています。これは2、3人にひとりは奨学金を利用しているということになります。
この水準は20年前の4倍近くにもなり、授業料の値上がりに加え、親世代の資金力が細っていることが原因です。
◼️奨学金返済を軽く考えてはいけない
返済延滞が3ヶ月以上続くと、個人情報が信用情報機関に登録され、住宅ローンやクレジットカードの新規発行や継続利用が難しくなる可能性が高くなります。
どうしても奨学金を返せないという場合、最終的な選択肢としては自己破産申請がありますが、親が連帯保証人になっている場合は親が返済を肩代わりしなくてはなりません。
このように、奨学金返済は自分の将来にとっても周りの人にとっても責任重大。
もし、失業や病気などの理由で返済が困難な場合は、返済期間を延ばす代わりに月返済額を半分か3分の1に減額できる「減額返還」や返済を通算10年停止できる「返還期限猶予」という制度を活用することもできます。
返済が困難になってしまったら、まずは相談。親に依存せず自分の問題として返済するようにしましょう。
◼️あえて借りておく、という選択肢
日本学生支援機構の3月の有利子・貸与型(第2種)は金利0.27%。
収支に余裕があれば繰り上げ返済をすることもできますが、これほどの低金利でお金を借りられることは他のローンではまずありません。
借入金利が低いという奨学金のメリットを活かすため、あえて繰り上げ返済をせず、借り入れを利用して月々の返済をしつつ、スキルアップや資産形成に取り組むという方法があります。
つまり、借入金利が0.27%なのであれば、繰り上げ返済に使うお金を運用に回して、0.27%を上回る運用益(利回り)を出せば結果的にお金は増えることになります。
「毎月返済しつつも、借入を利用して自身のスキルアップに励んだり将来の出費に備え資産形成に取り組む」ということが私たち若い世代が奨学金返済とうまく付き合うコツです。
_透過-1.png)