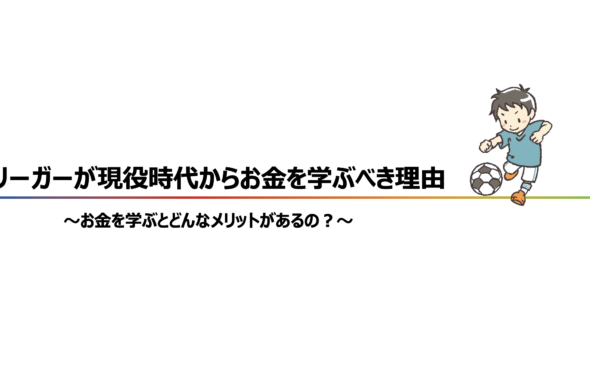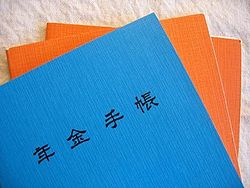
今の公的年金から考える私たちの未来
私たちの毎月の給料から引かれている「年金保険料」
しかし、誰しもが関わっているものであるものの年金について理解している方は意外と少ないのが現状です。
とくに若い方にとっては「今は年金もらわないし関係ない」と思われる方もいるかもしれませんが、年金は私たちが一生をかけて関わっていくとても大事なものであることに間違いありません。
本日は、そんな年金制度について簡単にまとめてそこからどう考えたら良いかを見ていきます。
◼年金制度は3階建て
まず公的年金とは、20歳以上のすべての国民が加入する「国民年金」と会社員や公務員が加入する「厚生年金」のことをいいます。
「1階部分」と呼ばれる国民年金(基礎年金)には自営業者や専業主婦を含め、20~60歳未満の約6700万人が加入しています。
「2階部分」の厚生年金は会社員や公務員(以前は共済年金でしたが、平成27年10月に厚生年金に一元化されました)の収入に比例した保険料を労使が折半して支払い、納めた保険料に応じた年金を受け取る仕組みになっています。
年金の受給に必要な加入期間は原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
「3階部分」には今話題のiDeCoをはじめとする確定拠出年金や厚生年金基金、国民年金基金などが該当します。
◼日本の年金の課題
日本の年金は現役世代が支払う保険料を高齢者の年金給付に回す「仕送り方式」(賦課方式といいます)の仕組みを採用しています。
少子高齢化が進むなかで制度を長期間維持するためには受給開始年齢の引き上げや受給額の抑制、現役世代の保険料の引き上げ等が避けて通れない状態になっています。
◼現状を知り、自分自身も対策を
現在、日本の年金制度は人口減少や少子高齢化により中身の充実どころか、制度の維持自体が非常に難しい状態です。
物価上昇や平均寿命の長期化、マクロ経済スライドによる受給額の減額が予想される一方、社会保障費や税金は増大していきます。
そのようなことを踏まえると、これからは私たち一人一人が自分の老後に責任をもって自分で対策をしていくことが必要不可欠です。
「適切な対策を取るための第一歩は現状を知ること」
これからの日本を生きる私たちだからこそ、まずは現状を知ることから始めて、自分の将来を真剣に考えてみる必要がありそうです。
_透過-1.png)