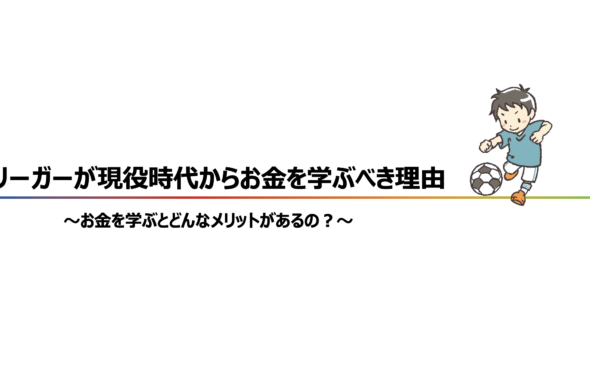これから結婚、出産する人に知ってほしい社会保障制度③~育児休業給付金~
20代後半に差し掛かり、私の周りでも結婚をしたり子供が生まれるという友人が増えてきました。
最近は妊娠、出産をしても、産休、育休を取得して会社に復帰する女性が増えています。
休職し、子育てに専念できることは素晴らしいことですが、その一方でご自身の収入のことが気になるという方は多いと思います。
そこで、今回は産休、育休中にもらえる社会保障制度にはどんなものがあるのか、3回にわたって紹介します。
3回目の本日は、育児休業給付金についてお伝えしていきます。
◼育児休業給付金を受け取れる条件
育児休業給付金は、育休中にもらえるお金のことです。
出産するときは「出産育児一時金」、生後8週間より前は「出産手当金」を受け取れるので、そのあとに受け取れる給付金です。
育児休業給付金は職場で加入している雇用保険から支払われます。
受け取るには、以下の要件を満たしている必要があります。
・育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している
・育休期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていない
・働いている日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)以下
正社員だけではなく、雇用保険に加入していれば、アルバイトやパートでも支給対象になります。
逆に、以下の場合は育児休業給付金をもらうことができません。
・雇用保険に加入していない
・妊娠中に育休を取らないで退職する
・育休に入るときに1年以内に退職することが決まっている
・1週間に2日以下しか働いていない
・育休期間中に給料が80%以上出る
・申請期限をすぎてしまった(育児休業が開始してから4ヶ月以内)
雇用保険に加入していないと、育児休業給付金を受け取れません。
そのため、専業主婦(主夫)や自営業者は支給対象外となります。
そもそも、育休は「子どもを育てるために、会社を休んでもよい制度」なので、退職した方や退職予定の方も対象外になります。
また、育休を取得しないで職場復帰をした場合でも、育児休業給付金を受け取ることはできません。
◼育児休業給付金の受給期間
育児休業給付金の受給期間は、育休期間と同じで基本的に子どもが1歳になるまでです。
しかし、保育園の抽選に落ちてしまったら、会社へ復帰できません。
もしそうなってしまった場合は、育児休業の延長手続きを行えば、子どもの年齢が1歳半になるまで延長することができます。
このときに対象になる保育園は、国が定めた「認可保育園」で「無認可保育園」の抽選に落ちても、育児休業を延長できないということは注意が必要です。
また、認可保育園の抽選に落ちたとき以外にも、育休を延長できるケースがあります。
その子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合、育児休業給付金の対象期間を延長することができます。
・死亡したとき
・負傷、疫病、身体上・精神上の障害により育児休業の申出にかかわる子を、養育することが困難な状態になったとき
・婚姻の解消や、その他の事情により、配偶者が育児休業の申出にかかわる子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定か、または産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間)
◼いくらもらえるのか
育児休業給付金は、最初の180日間と、その後で計算が変わります。
・育休期間開始から180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・それ以降
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
ここにある「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(産休を所得した方は休みに入る前)の6ヶ月の給料を180日で割った金額のことをいいます。(標準報酬月額ではありません)
1回の支給で2ヶ月分振り込まれ、1度手続きをしたらよいというわけではなく、2ヶ月に1度の頻度で支給手続きが必要です。
また、出産手当金と同じように、育休中は健康保険や厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料の支払いが免除されることもポイントです。
このシリーズでは、結婚・出産する人に向けた社会保障制度を紹介してきました。
今後も、私たちが生活する上で役立つ社会保障制度を紹介していきます。
_透過-1.png)