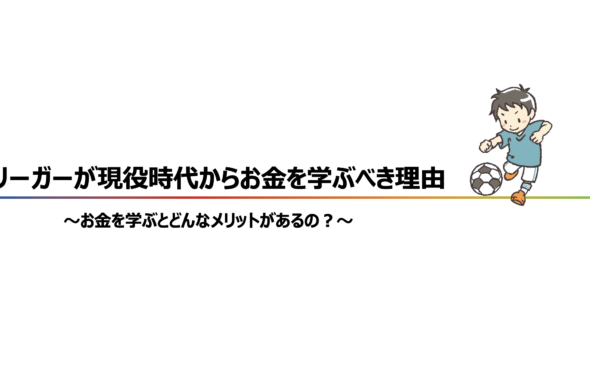死亡保険の前に、遺族年金を知ろう!
最近、私の周りでも子供をもつ方が多くなってきました。
それに伴って多く寄せられる相談のひとつに、万が一のことが起こった際の死亡保険はどれくらい備えるべきなのか、ということがあります。
たしかに、子供が生まれた段階で死亡保険を検討する必要はあると思います。
さらに、今は人生100年時代と言われるほど長生きする時代。子供が育った後の夫婦の将来の生活を考えて、どちらか一方が先立った後の暮らしのことも考えておくと無駄なく適切に死亡保険を検討することができます。
そのことを考える上で必須なのは、私たちが強制加入している年金です。実は、私たちは知らないうちに年金という保険に加入しているので、万が一の際には国から「遺族年金」という形で保障を受けることができます。
そこで、本日は遺族年金はどんな仕組みでどれくらい貰えるのかということを見ていきます。
■遺族年金には2種類ある
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」という2つの仕組みがあります。
自営業者など、国民年金の加入者が亡くなった場合に対象となるのは遺族基礎年金です。
もらえるのは子供がいる配偶者か、その子供自身で、18歳になると給付は終わります。
子供が一人前に成長するまでの助けという意味合いがあるためにこのような仕組みになっています。
一方、会社員や公務員など、厚生年金の加入者だった場合は遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が対象となります。
配偶者は子供の有無にかかわらず受け取ることができ、再婚しない限りは一生受け取り続けることができます。(夫死亡時に30歳未満で子供がいない妻は5年の有期受給になります)
もし、18歳未満の子供がいれば、前述の遺族基礎年金も同時に受け取れるため、会社員の方は十分な保障を受けることができます。
■どれくらいもらえるの?
遺族基礎年金は、年間約78万円の基本額に子供の数に応じた加算がつきます。
子供が1人なら22万程度が上乗せされ、約100万円。子供が2人なら45万円程度が上乗せされ約123万円。月額にすると8~10万円ほどになります。
遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の算定額によって異なってきます。つまり、勤続年数や収入によって人それぞれ受け取れる額には差があるということです。
人によって違うので一概には言えませんが、年間60万~100万円程度の遺族厚生年金を受け取っている方が多いようです。
ただ、遺族年金は年齢が上がるにつれて受け取る金額や中身が変わっていくことがあるため、単にその受給額を計算するだけでは不十分な場合があります。
例えば、遺族厚生年金とセットで設けられている仕組みとして、中高齢寡婦加算があります。
これは、40歳以上、65歳になるまで年間約58万円が加算されるものですが、子供がいるケースでは当初は遺族基礎年金を受け取り、18歳になった後は中高齢寡婦加算に置き換わります。
■社会保障で補えない部分を民間の保険に頼る
まとめると、万が一、一家の大黒柱の方が亡くなってしまった場合で子供が2人いたと仮定した場合、自営業者の方の場合は年間約123万円、公務員や会社員の方は年間約200万円程度のお金が遺族年金として受け取れることが多いようです。
さらに、投資用不動産を持っている方であれば、その不動産も遺族年金の役割を果たすことになり、保険で備えるべき死亡保険の金額はさらに少なくなります。
保険の加入を検討する際は、こうした社会保障でいくら備えられるのかを知ることは必ず必要です。
その上で、それでも足りない部分を保険に頼ることで無駄なく賢い保険加入ができるようになります。
_透過-1.png)