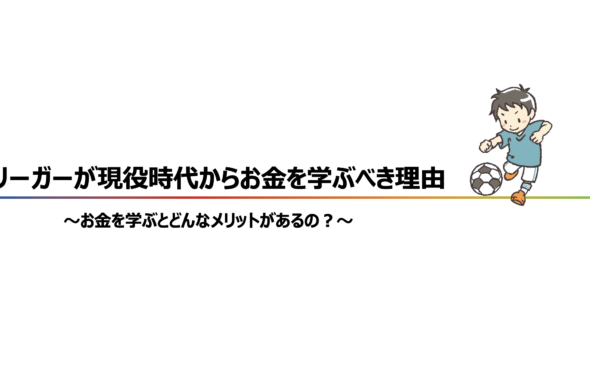時代遅れになったお金の常識3選
今回も記事を読んでいただき、ありがとうございます。
株式会社ワンクエストの中塚です。








子供が産まれたら郵便局や銀行の預貯金へ、もしくは積立型の保険に加入するという家庭も多いかもしれません。
昔は定額貯金でも年利12%だったり、積立型保険の予定利率も下図のように高かったため、何も考えずにただ金融機関に預けておけば、お金が増えるという時代だったからです。

(農協共済総合研究所レポートより 筆者再構成)

この時代に契約した保険は「お宝保険」と言われています。
しかし、バブル崩壊を機に金利は下がり続け、今では銀行預金の金利も0.001%ほどとなっています。
そのため、預貯金や積立型保険で資産形成を行う優位性は当時よりも薄れてきました。
昔は住宅ローンも金利が高く、借入金額が大きいほど利息が大きくなるため、
頭金をできるだけ多く入れることで、支払総額を少なくすることが主流でした。
今は借入金額が多くても、その分住宅ローン控除の恩恵で税金がお得になったり、
そもそも住宅ローンの金利が安いため、手元資金はできるだけ残しておいて、そのお金で自分で運用を行うほうが期待リターンが大きい場合もあります。

また、住宅ローンを組んでから年数が経っている場合は、借り換えを検討しましょう。
一番安い金利の金融機関はモゲチェック等のサイトで簡単に確認できます。
昔は「株は素人手出し無用」や「投資信託は手数料が高いから損する」という話を聞くこともありました。
これは正しい投資手法を知らずに感情に任せて取引を行い失敗したり、営業マンの進めるがままに手数料の高い投資信託を購入したことで資産が目減りしてしまったことが原因と考えられます。
また、売買手数料の低いネット証券や、NISA等の税制優遇がなく、個人が情報収集して投資を行うハードルが高かったことも原因の一つです。

今では、国が「預金から投資へ」のスローガンを打ち出し、金融機関でも手数料の安い投資信託の取り扱いが増えたりすることで、個人が投資を行う上で有利な環境が整ってきました。
ちなみに、知識のないままノリで行う「投機」は今昔ともに危険です。
きちんと知識をつけてから行う「投資」は、資産形成の観点からも、企業の成長を応援するという観点からも、ぜひ取り入れていきたいですね。
いかがだったでしょうか。
他にも、医療保険の見直し頻度やキャリア形成、老後資金など、数十年で常識が変わったことは沢山あります。
日本では家庭や学校で金融教育が行われる機会が少なく、お金と向き合うことが悪・卑しいとされる風潮があるため、古い常識のままアップデートされていないことも往々にしてあるようです。
ダーウィンの進化論でもあるように、生物は環境の変化に適応できる個体が生き残ります。
これからの時代を生き延びるためにも、時代に合ったお金への向き合い方を考えていきましょう!
_透過-1.png)