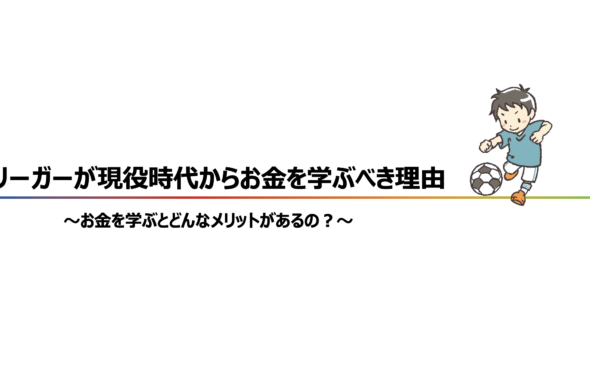知らないと損する!申請するだけでもらえるお金
今回も記事を読んでいただき、ありがとうございます。
株式会社ワンクエストでコンサルタントをしている柿本です。




【申請するともらえるお金】
①育児休業給付金
②結婚助成金
③高額療養費制度
特に上記3つあたりは、生活に密接に関わる給付金かなと思います。
順番に見ていきましょう。


こんな条件に当てはまる人がもらえる給付金だよ。
大前提として「雇用保険への加入」が必須なので、退職をするともらえなくなります。
また個人事業主も受給できないので、独立を考えられている方は出産や育児のタイミングを考えて計画しましょう。


【休業した8週間後〜6ヶ月目まで】休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
【6ヶ月経過後〜子どもが1歳になる前日まで】67%→50%に変動
「休業開始時賃金」というのは、育児休業を取る直前の6カ月間の給料を180日で割った金額を指します。
また手取り金額ではなく、住宅手当や交通費など各種手当を含んだ額面金額です。ただ、ボーナスは含まれないため気をつけましょう。
賃金日額が1万の場合、6ヶ月間は20.1万円、6ヶ月以降は15万円程度の給付があります。

結婚助成金は平成30年から少子高齢化対策として始まった、新婚生活を支援するための制度です。
いくつか気をつけなければいけない点があるので、みていきましょう。
【注意点】
❶補助の対象になるのは、新居の住居費や引越し費用に限られる
❷必要書類が多い
❸すべての市町村で受給できるわけではない
新居の住居費とは、新居の購入費や新居の家賃の1ヵ月分、敷金・礼金や共益費の1ヵ月分、仲介手数料を指します。
引越費用は、引越業者や運送業者にかかった費用、荷造りのための費用で、この合計金額が対象になります。
また補助率は50%なので、申請した金額の半額が補助される仕組みです。
①補助金交付申請書
②婚姻後の戸籍謄本
③入籍後の住民票
④世帯の所得証明書
⑤新居に関する書類(賃貸借契約書など)
⑥市県民税の滞納がないことを証明する書類
⑦補助金交付請求書
⑧新居の住居費や引越しの領収書 など
その他自治体によって必要書類が異なる場合があるため、各自治体のホームページや窓口で確認をしましょう。
また年齢や所得によっても制限が設けられているため、適応になるかどうかもきちんと確認しましょう。
ちなみに東京では給付されう自治体がないので、今後出てくることを願いましょう・・・。



高額療養費制度とは?
医療機関の窓口などで支払う自己負担額が所得や年齢に応じて決められる自己負担上限額を超えたときに、負担を軽減する制度。

引用:https://www.rakuten-insurance.co.jp/media/article/2020/079/
つまり窓口で30万円ほどかかっても後から申請すると、お金が返ってくるという制度です。
この制度を知らずに、民間の医療保険に過剰に加入してしまっている方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?
また出産のようにある程度事前に時期がわかっている場合や、入院が長期化した場合は「限度額認定証」を取ることをお勧めします。
限度額認定適用証とは?
通常一度窓口で3割負担分の医療費を満額支払い、その後高額療養費制度を利用することで差額が還付される流れです。
しかし「限度額認定証」を取得することで、窓口での支払いに高額療養費制度が適応となるため、還付される分を支払わずにすみます。
結局支払う金額は同じなのですが、一度もキャッシュアウトしないで良いのであれば、嬉しい方も多いのではないでしょうか。
高額療養費制度も限度額認定適用証も、原則申請しなければ受けられない制度になっていますのでご注意ください。
結婚、出産、住宅購入、さまざまなライフイベントがある中で出てくる不安はその時々によって違います。
また残念ながら、そういった不安は実際に出てきてからしか真剣に悩むことがありません。
「急ぎたいけど、焦って誤った選択をしたくない」という方も多いはずです。
そんな時1つの会社の商品、提案だけでなく、幅広い商品や経験の中からご相談に乗れる独立系FPを頼ってみてください。
「結婚したら、子どもが産まれたら保険に入った方がいいの?」
「住宅ローンは繰り上げ返済した方がいいの?」などの不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談くださいね。
_透過-1.png)